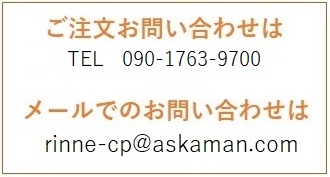1�|�n���ɗD�����u�ۍk�_�@�v�Ƃ�
2�|�ۍk�_�@�g�}�g�̂��Љ�
3�|��ؗނ͔̍|
4�|�k�C�����a���ɂ�������������ރA�X�J�}���Q�P�E�b�̎{�p�̌�
5�|���쌧�����i�����q�����j�F�ۍk�_�@�ɂ�郌�^�X�̍�
6�|���a�n��̃������E�X�C�J�E����ѐ���ł̎��g��
|
�@�@
|
�@ |
�@�@
|
�n���ɗD�����u�ۍk�_�@�v�Ƃ�
|
�u�ۍk�_�@�v�Ƃ��D�E���C���ۂ𗘗p���āA�L�@���i�Δ�A���A���~�K���A�o�[�N�A�͔�Ȃǁj���z���������Ƃɂ��A�y��̔敾�E��h�~���A�n�͂��ێ��E���コ���A�_�Y���̈��萶�Y����������V�����_�@�ł��B
�@�܂��A�ۍk�_�@�͑����̔����q�̒c����e�Ղɍ�邱�Ƃɂ��A���₩�ɍ��x�ȓy�����������܂��B�c������R�ł���Ɩ{���̓y���̑_���ł���@�������A�A���w���C�B�������i��dgc�����ł̃o�C�I���O���͌��ʂ���j�����P����܂��B
���ɁA�B�̐������͍D�E���C���ۂ̑�����ʂɂ��A�y�뒆�ɂ������������̋ۑ��������P���܂��B�������̑��l���Ɗ��������i�i�Ɍ��シ��ƁA�A���Q���y����ō܂��g�p���Ȃ��ő啝�Ɍy�����܂��B�܂��ɁA���ɗD�����ۍk�_�@�ł��B
|
[�����q�c���̌���]�F
�\�ʐς��啝�ɑ�����̂ŃC�I���̗͂Ń~�l������엿�����������悭�z������܂��B�r�����E�ې����E�ʋC�����悭�Ȃ�̂Ŕ����̍������L����A���т������܂��B |
[�i���E���̌���]�F
���������тɂ��{�����L�x�ɋz���ł���̂ŁA�������������ƂȂ�A���Ă̓^���p�N�ܗL�ʂ�����A�H���l���オ��܂��B��ؗނ͐A���̓��̏Ɏ_�����悭��ӂ����̂ŊÖ��������A���_�o�����X�����P����A�זE���k���ɂȂ�̂œ��������悭�Ȃ�܂��B |
[���i�������オ��]�F
����̓��L�i�������f��}���j���N�����Ȃ��ŁA�����[������A���ʂ������A���������Ȃ�̂œ|������A������Q���Q�ɂ��ς����܂��B�܂��A��������o�n����̂œ������オ��A�����܂肪�ǂ��Ȃ�܂��B�t�ؗނ͍����悭����̂ŁA�{���̋z�����悭�K�i�������܂��B�ʍؗނ͍זE���k���ɂȂ�̂ŏd�݂������u�i���E��������v���ʂ����҂ł��܂��B���ؗނ��Δ��A�X�J�}���͔�̘A�p�ɂ��A���Q���y������܂��B |
|
�@ |
�@�@
|
�ۍk�_�@�g�}�g�̂��Љ�
|
���i���F |
�Ȗ،��F��Y���i���@�g�@�}�@�g |
�͔|�F |
�ږȂ������ł��u�ۍk�_�@�v�ɂ��B |
�y����F |
1�L�@���ƌ͑��ۂȂǂɂ���g�L���ȓy�h�����B
�y����ō܂���؎g�p�����A�y��̋ۑ������߂�B |
�i���F |
�������ɂ��y����Ԃ�̂ŁA�����ǂ�����A�������������ƂȂ�̂ŊÖ��������A���_�o�����X���悭�Ȃ�B |
���Y�҂������҂̊F�l�� |
�g�����͔|�̂��߁A�N�ɂ������Ȃ����i��i�j�ƁA���M�������Ă����߂��܂��B�h |
|
|
|
|
|
�ۍk�_�@�F�D�E���C���ۂ𗘗p���ėL�@�����z�����邱�Ƃɂ��A�L���ȓy�����A�_�Y���̈��萶�Y����������_�@(sustainable farming)�B |
|
|
�@ |
|
��ؗނ͔̍|
|
�D�E���C���ې��܃A�X�J�}��21�͗Δ�A�����A���~�K���A�o�[�N�͔�Ȃǂƕ��p���������ނƓy��̒c�����𑣐i�A�������̋ۖ��x�����߂܂��B
�A�p����Ɠy���z�J�z�J�ɂȂ�A�k�Ղ�����������q�̒c������R�ł��A�ۖ��x�����܂�̂Ńt�U���E���Ȃǂ̑��B��}���܂��B
�@���̂��߁A�}�j���A���ǂ���g�p����Γy����ō܂��g��Ȃ��Ŗ�ؗށE�ԗނȂǂ̘A���Q���瓦����܂��B�����q�̒c���̕\�ʐς�������̂Ŕ엿������~�l�����̃C�I�����z������CEC(����u���e��)���傫���Ȃ�܂��B�܂��A�c���ɋz������Ȃ��C�I��������̂�EC(�d�C�`���x)��������܂��B
�@���ʂƂ��āA�엿�̎{�p�������オ��A�������������ƂȂ�̂Ŗ�ؗނ̗t���̏Ɏ_�����������܂��B�A���̂̍זE�̖��x���ׂ����Ȃ�A�Ö��������A����������ؗނ���R�̂�܂��B�ԗނ͐F���N�₩�ɂȂ�A���������܂��B
���쌧�������E������������
�g���^�X�A�u���b�R���[�A�J���[�t�����[�Ȃǂ̖�ؗނ��u�ۍk�_�@�v�ō͔|����8�N��
�ɂȂ�܂��������悭����̂ŘA���Q�͈�؏o�Ă��܂���B
�@ |
|
�@�@
|
�k�C�����a���i�����@�����j�ɂ�������������ރA�X�J�}���Q�P�E�b�̎{�p�̌�
�\����E�������E�X�C�J�\
|
�P�D���c�p�A�X�J�}���Q�P�b
|
�y����1�z
���Ɣ̔���p�ɑI�i��u����Ђ߁v���S�O�A�[���̐��c�ŁA�����Q�R�N����A�X�J�}���Q�P�b�������I�Ɏ{�p���Ă݂����ʁA�~�t���d�߂ŁA�͂ꍞ�܂Ȃ��A�|�����ɂ����B�܂��A�i���ʂł͗����肪�ǂ��A���q����͔��������ĐH�ׂ₷���Ƃ��������������Ă����A�Q�U�N�x���p���{�p�������ʓ|���h�~�܂��g�p���Ȃ��Ă��|��Ȃ����Ƃ������ꂽ�B
�y����2�z
�����Q�Q�N����n�߂��B���߂̂Q�N�Ԃ͂S�O�A�[���Ŏ{�p�����B���ʁA�Q�R�N�x�́A�~�t�������炵�炭�̊ԁA�ܓV�������A�K���ɂ������a�̗\�h���ł��Ȃ��������߁A�������a�����\�N�U��ɑ唭�����Ă��܂��B����ȏ��őΏƋ�Ɣ�r���Ă݂��Ƃ���A�������a�̒��x�����Ȃ��A�|���̒��x�����Ȃ������B�܂��A�H���ɂ��Ă��A���q����̕]�����ǂ������B
���ʊm�F���ł����̂łQ�S�N�x����͂P���S�ʐρi170a�j��13kg/10a�̊����ŎU�z�����������ʁA�Ώۋ���|�������炩�ɏ��Ȃ��A�s�t���d�߂ō����肪�ǍD�Ɋ������B���n�ʂɂ��Ă͓V��Ɍb�܂ꂽ�W�����邪�A�Q���N�Ƃ��P�O�U�O��ʼnߋ��ō��̏o���ƂȂ����B
�H���̕]�����ǂ������̂łQ�U�N�x����͕ʂ̕ޏ�ł���r���������Č��ʂ��m�F�������Ƃ���A�|���h�~�܂��g�p���Ȃ��Ă��|��Ȃ������B���N���L��ł��ꂩ����ł��B���c�p�A�X�J�}���Q�P�b�{�p�̉ۑ�͏H�Ƀ��~�K��600kg/30a�������ɏȗ͓I�ɎU�z���邩�ł��B�܂��A��y�̒��ԁi�\�����j����N60a�{�p�������ʂ��ǂ������i��������N�������P�U�قǑ��������j�̂ŁA���N�͈�C��15ha�Ɏ{�p�����Ƃ��덪������Ȃ��A�|���������A��L��ł������B
|
�Q�D�������̕a�C��ƃA�X�J�}���ۂɂ���
|
|
|
�n�E�X�͔|�̏ꍇ�A�����͔|����}���͔|�I���܂ł̊��Ԃ���Q�O�O���Ԃ���A���ݍs���Ă���A�L�@�엿�ƒ��n�͔�A�ێ��ނ��U�z���ă��[�^���[�ŋN�������@�ł́A2��ڂ̕s�k�N�}���͔|�̌㔼�ɂ́A���n�͔�̕������w�ǏI����āA�A���Q�̏Ǐ����o�ė��邱�Ƃ�����܂��B25�N�x�̗}���͔|�̂q�|�P�P�R�������̈ꕔ�̃n�E�X�ł������_�a�̌y���Ǐo�܂����B����͒������̂���o�[�N���ނ��������邩�A����������ꍇ�͕ʂ̕��@���Ȃ����A�ŊJ��̕K�v���������Ă���܂��B
�܂��A���̂������_�a�ɂ��ẮA24�N�ɂ��̕a�C�ŋ�J�����Ă��郁���o�[2�l���A24�N�̃��������n��ɁA���k�͔�ƃA�X�J�}���Q�P�̓K�ʂ��Z�b�g�Ŏ{�p�������ʁA25�N�Y�̃������̖���s�t�̏�Ԃ��㔼�ȍ~���A���Ȃ���P����A���I�����ǂ��Ȃ����̂ŁA������p���g�p���Ċώ@�𑱂��邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
���́A�������_�a�̕a���E�B���X�́A�������������_�E�B���X�ŁA�`�t�`������ƂƂ��ɁA�y�뒆�ɐ�������Ð��ۗރl�R�u�J�r�ڂ̑��ۗނł���I���s�f�B�E�����ۂ̈�킪�}���y��`�����a�Q�ł�����܂��B
�������₷�������Ƃ��ẮA���n�ȃo�[�N�͔����k���ʂɎU�z���Ă��܂����Ƃ�Ȃ�������A�Z�ނ�A�삵����A���ƕs���Ƒ����d�Ȃ�����ApH�����������肷��Ɣ��a����������悤�ł��B
�h����̕��@�́A�F�X����Ǝv���܂����A���́A�A�X�J�}���ۂ��L�@�������鎞�ɕ��傷����LP�̗͂����p����̂���ԗL�����Ǝv���Ă��܂��B�����A�Q�P�N�x����A�n�E�X��̂Ɏ{�p�𑱂��Ă��܂����A�����Â��ʂ��o�Ă��Ă��܂��B
(��)�@LP�Ƃ̓��|�y�v�^�C�h�Ƃ����E�ʊ����܂Ŏ���ۂ�}�����܂��B
��̓I�Ɍ����܂��ƁA�A�X�J�}���ۂ�K�ʎU�z���邱�ƂŁA�������A�X�C�J���̃}���`���̎_�f�̏��Ȃ�����Ԃł��A���n�̑@�ێ���앨�c�ԓ����K�ʍ�������Ă���ƁA�@�ێ�������i���C���ہj�Z�����[�[�̌��ʂƁA�J�r�ނ�}������i�D�C���ہjLP�̑�����ʂœy��̒c���w�����P���邽�ߍ�y�w�̊������P����A�앨�̍����肪�ǂ��Ȃ�܂��B���̌��ʁA�앨�����S�ɐ��炵�܂��B�@�@�Ƃɂ����A�g�������H�v���邱�ƂŁA���ʂ�����ɃA�b�v�������ȋێ��ނȂ̂ō�����A��p�Ό��ʂ���������Ɣ��f���A����̎��s�͈͂��l���Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B
�R�D���p�u�A�X�J�}���Q�P�v�ɂ���
������21�N����͔|�n�E�X��̂Ŏ{�p�J�n
����21�N��1���Ɂu�ۍk�_�@�v�̘b�ɏo����Ƃ��o���܂����B���̌�A�����Ȃǂ��������ʁA���e�ɂ��Ă����m�ŁA���܂ł̔��������ނƂ͈��������������A�D�C���ہA���C���ۂ̗��������܂����p���邱�ƂŁA�R�X�g�_�E����}��Ȃ��猸�_��A���엿�͔|������Ɖ\�ɂȂ�A�A���Q�����������P����悤�Ȃ̂Ōp���g�p���Ċώ@�𑱂��Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B
�̂����ʓI�ɍs���Ă����y�����@�́A���n�͔�̓�������{�ł��������A�����ۍk�_�@�̓p���[�̂��钆�n�͔����n�c�ԕ��ڕޏ�ɎU�z���āA�y��̒c���\���̉��P�ƍ���肪�����ɂł������܂łƈ�����_�@�Ȃ̂ŁA�܂��͎��ۂɐF�X�ȕ��@�Ŋ��p���A�̌����Ă݂Č��ʂ��m�F���A�g�p�͈͂������ł��g�傳���čs�������Ǝv���Ă��܂��B
���̏ꍇ�́A�͔|�n�E�X�̓y���̂��߂̊��p�����C���ł���A���n�͔�ƗL�@�엿�ƃA�X�J�}���ۂ��Z�b�g�Ōp���g�p���Ă��܂��B�܂��A���k�͔����A��c�p�̏��y���ɂ����p���Ă��܂��B���̑��ɂ��������n�E�X�̈ꕔ�̍�^�ɏH����������Δ�p�Ƃ��Ď������N�̂U���ɃA�X�J�}���ۂ��T���ăX�L���݁A�������������ɒ�A����ꍇ�i�A�X�J�ۂ͈����L�@�_���o���Ȃ��j�ɂ����p���Ă��܂��B
�ʏ�͈ꊔ������4��肪��{�ł����A�Δ�Ƒ͔�ƃA�X�J�}���ۂ��Z�b�g�Ńn�E�X�̓y�����s���悤�ɂȂ��Ă���́A�ꕔ�̍�^�ŁA�ꊔ������5���ʂ����Ă����i�������������n�ł���̂ŃA�X�J�}���ۂ̌��ʂ�������x�������Ă��܂��B
������_�ʂ̎g�����̎���Ƃ��ẮA���N�A�n�E�X�����ɁA���k�Ë����{�H���A�A�X�J�}���ۂ̌��ʂ��ώ@���Ă��܂����A�lj��̒��f�ʂ��K���ł���A�X�J�}���ۂ̑��B��2�N�ȏ㑱���悤�ŕޏ�̔r����Ɠy���ɂ́A���Ȃ�L���ȗ��p���@���Ǝv���Ă��܂��B
�����A�A�X�J�}���ۂ��g�����Ȃ����߂ɂ́A�������̉ۑ������Ǝv���Ă��܂��B
��قǂ��q�ׂ܂������A�D�C���ۂ̃o�`���X���ۗނƌ��C���ۂł���N���X�g���W�E�����ۗނ����ɗ��p�ł���l�ȗL�@���̓������@�łȂ���Ό��ʂ��ő���ɗ��p�o���Ȃ��킯�ł��B���̂��ߍ͔|�̌㔼�܂ł������ƕ������i��ł����悤�ɗL�@���̎�ނ̑I���Ɣz�����������A�앨�͔̍|���Ԃɍ��������̂𓊓����Ȃ���ő���̌��ʂ������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă��܂��B
������F������̏����Q�l�ɂ��āA�A�X�J�}���ۂ̌��ʓI�Ȍp���g�p���@������ɒNj����Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B
�i���j
�@ |
|
�@�@
���쌧�����i�����q�����j�F�ۍk�_�@�ɂ�郌�^�X�̍�
|
�@�@
|
| �@ |
|
���a�n��̃������E�X�C�J�E����ѐ���ł̎��g��
|
�P�D���p�u�A�X�J�}���Q�P�v�̊��p
|
���B���a���̃O���[�v�́A����6�`�V���ŋۍk�_�@�����p�����Ē����Ă���܂��B
�܂��A�����o�[�S�����A�炢�ł�ʕ����Y�g���ɉ������ĉZ�ނ͔̍|�𑁂����瑱���Ă��܂��B���ݑg���ł͑��i�ڂ͔̍|���s���Ă��܂����A�Z�ނ̋K�͂́A�X�C�J�A�����������킹��190���Ŗ�S�O�Oha���͔|�𑱂��Ă��܂��B������������u�A���Q��v�Ƃǂ����������Ă����悢���A�d�v�ȉۑ�Ƃ��Ď��g�݁A�Ή���Ƃ��āA��ʔ���Ɠ����悤�ɗ֍�̌n���\�ɂ��邽�߁A�ړ��\�ȃx�g�R���n�E�X����������������܂����B
���̌��Ɛ��ɖ�肪����Œ莮�̑�^�n�E�X���嗬�ɂȂ�܂����B��^�n�E�X�͔|�͗֍�̌n��g�ނ̂�����A�A���Q�̖�肪�o�Ă��܂��B���̖��ɒ��ʂ��������́A�ǎ��Ȋ��n�͔�̓�������ԗǂ����@���ƍl���A�n�͑��g���𗧂��グ�A��K�͂ȑ͔쑢�������ēy������������������܂����B�͔쓊���̑��Ƀl�M�ނ̍��A����������ނ̓����@�X�ɉ��w�엿���ł��邾�����炵�āA�L�@�엿��̂̔�|�Ǘ��ɐ�ւ��Ĉ��S�A���S�Ȑʕ��̐��Y�ɓw�߂Ă��܂����B
���̌��ʂ�����x���P���܂������A��Q�̌��ƂȂ�L�Q�ȃJ�r�ނ�E�C���X�A�ہA�������̖��x��������悤�ȑ�́A�F�X�ȕ��@�ōs��Ȃ���Γ�����낤�ƍl���Ă��܂����B�܂��A�������̑ŊJ��̈�Ƃ��āA�F�X�ȍu�K��⍧�k��ɎQ�����Ă��܂����B
���܂��܁A�����Q�P�N�x�̑�P�T��ڂ̓y�Â��荧�k��̐Ȃŕy�c������u�ۍk�_�@�v�̏Љ����A���e���Ĕ��ɋ����������A���̌㒇�ԂƂƂ��ɕy�c��������������J���A�����������������ʁA�y�Â����A���Q�̌y����A���萶�Y��Ƃ��Ď��ۂɎ��g��ł݂鉿�l���\������Ɣ��f�����̂ŁA�Q�P�N�̏t���燋�A�X�J���V�В��̃A�h�o�C�X���Ȃ��琔�l�Ŏ��g�݁A��V�N�o�߂��Ă��܂��B���̊������Ԃ�������Ǝv���܂��B
|
�P�j���p�u�A�X�J�}���Q�P�v�̊��p
|
���B�̒n��ł̓n�E�X�͔|�̏ꍇ�A�{�݂̗L�����p�Ɣ_�Ə����̈����ڎw���ĉZ�ނ�N�ɂQ��͔|���邱�Ƃ������A���̂��ߏ����̈����ޏ�قǘA���Q�̃��X�N�����܂�A�F�X�ȏǏo��ꍇ������܂��B�����Q�O�N���܂ł͗ǎ��͔�ƐF�X�Ȕ��������ނ�E�ۍܓ��łȂ�Ƃ��X�C�J�A�������̘A��𑱂��Ă��܂������A��p�Ό��ʂ̖ʂŁA�ۑ��������ɋꗶ���Ă��܂����B
���̌エ�A�l���u�ۍk�_�@�v�ɂ��y������ɏo����Ƃ��o���A���̌���A�h�o�C�X���Ȃ���F�X�ȏ�ʂ��A�X�J�}���ۂ��g���Ă݂܂����B�p���{�p�������ʁA�X�C�J�A�������̐����ԁA���Ɏ��n�߂��̖��̏�Ԃ��ȑO��肵�����肵�Ă��Đ��i���������Ȃ����Ɗ����Ă��܂��B�����̌��ʂ̗v���́A���n�͔�ƃA�X�J�}���ۂ̌p���{�p�Ńn�E�X�y��̋ۑ��̉��P�i�������̉��P�j�ƁA�y��̒c���������i�i�������̉��P�j���ꂽ���߂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă��܂��B
����X�Ɍ��ʂ��p������悤�u�A�X�J�}���ۂ����p���A���n�͔�̂������݂ɂ���y�����y���������v���ő�����p�o����悤�ɂ��邽�߂ɁA���ɂǂ̗l�Ȋ��p���@���l�����邩�A������p�x����\����Njy���Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B
|
�Q�j�͔���͒��n���x�X�g
|
�ۍk�_�@�ŗ��p������������ނ́A�A�X�J�}���Q�P�́A��������o����Ă�����������ނƂ͈قȂ�ۂ̒��g�i��ށE�|�{�E�戵�����@�j���͂����肵�Ă���B�D�C���̃o�`���X���ۂƌ��C���̃N���X�g���W�E�����ۂ��o�����X�ǂ��P�O��ގg�p����Ă��ĂP�O��ނƂ��[�I���C�g�ɖE�q�̏�Ԃŋz�����Ă���A�����������ƁA�ǂ�ǂB���ăZ�����[�[����ƁA�iLPs�j���|�y�v�^�C�h (�E�ʊ�����)���哙�̑�����ʂŗL�@������ɑ����������A�L�Q�Ȏ���ۗނ�}�����ċۑ��̃o�����X��ǂ����A�y��̒c�����E���P����\�͂�����悤�ł��B
���͖��N���݊k���R�O��i�P�Q�O?�j�قǏ����Ă��炢�A��Q�O���̒{�ӂ�͔�ƍ������AC�^N����R�O�`�S�O�ɋ߂Â��邽�߂ɒ��f�엿���U�z���A�\�����ČÃr�j�[�����|���Ă����܂��B���k�̊����������ꍇ�͐����������K�v�Ȃ��߁A���N�̂U�`�V���ɒlj��̒��f�엿�ƃA�X�J�}���Q�P���������A�\�������Ĕ��y�𑣂��܂��B
�P�O�����ɂ̓p���[�̂��钆�n��Ԃ̖��k�͔����o���オ��܂��B�A�X�J�}���͔�̖��͂́A�u���������������Ԃ���w�ǂ��Ȃ��i�ȗ́j�ōD�E���C���y������B���x�͂U�O�x�Ŏ~�܂�i�ȃG�l�j�ALPs���ʂŔ������ɂ�键�y�����������Z���Ԃŗǎ��Ȓ��n�͔�����邱�Ƃ��o���邱�Ƃł��B�v�i�]���̊��n�͔���͉������Ԃ����čD�C���y�����邽�ߍ����ɂȂ�ꕔ�́u�R�������v�ɂȂ�ꍇ������A���������n����قǒc���w�����͂��キ�Ȃ�B�j�@�܂��A�n�E�X�ɂ��́u���݊k�͔�v���������ގ��̓������̖������n�c�Ԃƕčf�A�J���V���E�����ށA�A�X�J�}���Q�P�̓K�ʂ��ɂ������ނ悤�ɂ��Ă��܂��i�n�E�X�F�U���~�P�O�O���~�R�O���j�B
|
�R�j�������������_�a��
|
�a�Q�̕a���E�C���X�́A�������������_�E�C���X�ŁA�`�t�`������ƂƂ��ɁA�y�뒆�ɐ�������Ð��ۗނ̃l�R�u�J�r�ڂ̑��ۗނł����I���s�f�B�E�����ۂ̈�킪�}���y��`�����a�Q�ł�����܂��B���̗l�ȓy��a�Q�ɂ��u���n�̃A�X�J�}���͔�̌p���{�p�œy�����y�����邱�Ƃɂ��v�����̃J�r�ނ�}������̂ŁA�u�������_�a�v�̌y����ɂ��Ȃ�L���ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
�܂��A�y��a�Q�̗}����Ƃ��āA��삵�����n���Ȃ��^�C�v�̃n�E�X�́A�~�͂�ɋ������C���M�������āA�K�ʂ̃A�X�J�}���ۂƈꏏ�ɂ������݂R�`�T����i�s�V�E���ۂ�}�����A�������������߉\�j�ɂ̓������̒�A���s���܂��B���̂悤�ɗΔ�앨�ƈꏏ�ɒ��n�͔�ƃA�X�J�}���Q�P���������ނƋۂ̗����オ�肪�������ʂ��A�b�v����悤�ł��B�܂��A���̃^�C�v�̍�^�̃������n�E�X�́A�������B���邽�߈ȑO��芔���������������i�P���S�ǂ肩��T�ǂ�j���ʂ����Ă��w�ǖ��Ȃ��A���ʂ��������Ă��܂��B
|
�Q�D���c�p�u�A�X�J�}���Q�PC �v�̊��p
|
����22�N����p���{�p���Ă��܂����A���߂̂Q�N�Ԃ͂S�O�A�[���Ŏ����{�p���A�ώ@�𑱂������ʁA�ϕa���A�ϓ|�����A�i���Ǝ��ʐ��A�X�ɂ͂Q�O���߂�������\�Ȃ��Ɠ����ʂ��m�F���邱�Ƃ��ł��܂����B���̂��߁A���X�ɖʐς𑝂₵�Q�U�N���琅�c��t�ʐς̖�V�T�����u���c�p�A�X�J�}���Q�PC �v���P�O�A�[��������P�R�L���̊����Ő��c�엿�ƈꏏ�ɎU�z���Ă��܂��B
�A�X�J�}��21C �̌��ʂ��ő�������o�����߂ɂ́A���m�ƓK�ʂ̖��k���������ƕ������i�ނ悤�Ȏ��ނ������U�z����ق����ǂ��킯�ł����A���̏ꍇ�́A��Ԃ̊W������A�����蒼��ɐ��m��������ނ����ŐF�X�Ȍ��ʂ��������Ă��܂��B���ɁA�ϓ|�����ɂ��ẮA���̃A�X�J�}���ۂ��g���n�߂�O�܂ł́A�R���o�C��������8�N���Ŕ��ɌÂ���\�͂̂��߁A�|�����₷���y���̐��c�ɂ́A���N�A�|���܂̃r�r�t�����U�z���Ă��܂������A�A�X�J�}���Q�PC�̎{�p�J�n�Ɠ����Ƀr�r�t���̎U�z���~�߂Ċώ@�����Ƃ���A �����肪�ǂ��Ȃ����������A�ȑO���s�t���ł߂ɐ��炷�邽�ߓ|����肪���Ȃ���P���ꂽ�Ǝv���Ă��܂��B�܂��A�����ɐ��������ƐH�������Ȃ���P���ꂽ�Ǝ������Ă��܂��B
����27�N�x�̐��������ɂ��ẮA���a���S�̂ł��ɒ[�ɗǂ��N�������̂ňٗ�̔N���Ǝv���Ă��܂����A��N�ł���A�����Ă̊�����5���O��ł����A27�N�x�͉ߋ��Œ�̖�1���ł����B�����20���ʂ̌���i�ȃR�X�g�j���ێ����Ȃ���A�X�J�}��21C���p���{�p���āA���肵�����ʂ���̂��m�F�������Ǝv���Ă��܂��B
|
�R�D���C�G�L�X�̊��p
|
�����Q�P�N�̂P���ɋۍk�_�@�̏����A���̔N�̂R���̈�c���玎���U�z���n�߂Ă��܂����A�����Ɍ��ʂ��m�F���邱�Ƃ��o�������߁A�l�X�ȏ�ʂŌp���{�p���Ă��܂��B����܂Ŏg�������ώ@�����Ƃ���A���̏�Ԃ��ȑO��萨�������蔒�����B���Ă��邱�Ƃ��킩��A��c��������n�I���܂Ŏg�������Ă��܂��B���Ɉ�c���Ԃ́A�P����{�̃l�M�̔d�킩��n�܂�A�V����{�̍ŏI�}���������d��܂ő�����킹��ƂP�T��ȏ�d�킵�܂����A�ȑO�͈�c�̌㔼���ɂȂ�ƐF�X�ȕa�C�ŕc�̕����܂肪���������̂ł����A���C�G�L�X���g���悤�ɂȂ��Ă���͗����͂�a�⍪����a���̑��F�X�ȕa�C�̔��������ɏ��Ȃ��Ȃ�Z���Ԃŗǎ��ȕc���ł���悤�ɂȂ���ʂ��������Ă��܂��B
���C�G�L�X�̔Z�x�ɂ��ẮA�|�b�g���g���܂킵���鎞�́A�c�̔��グ�R���O���ɂP�O�O�{�ł����Ղ�A�d�펞�ƕ��ʟ��͂Q�O�O�`�R�O�O�{�şA�_��U�z�̂Ƃ��͓W���܂̎g�p����߂đ���ɃG�L�X���R�O�O�{�ʂō����A�����c�̗����͂�a���̑��̗\�h�ɂ͂Q�O�O�`�R�O�O�{�A�����I�ɕa�C���m�F���ꂽ�ꍇ�͂P�O�O�{�O��ł����Ղ���ĕa�C���L����Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B
�͔|�n�E�X�̟`���[�u�ɗ����Ƃ��͈�x�ɂT�O�O?�ʍ��ɍ��킹�ēK�ʍ������܂��B�܂��A��ؐ�p�n�E�X�̏ꍇ�͂P�O��ވȏ�̖���͔|���āA���������~���܂Ŏ��n�𑱂��邱�Ƃ��e�Ղł���A���̌シ���ɂ��ׂĂ̎��n�c�ԂƑ��߂̃A�X�J�}���͔���������ނ��߁A��A������n�����܂ő��̍앨��茳�C�G�L�X�𑽂��g���܂��B���ӓ_�Ƃ��āA���̃G�L�X�͎����ō��A���ʂ��m�F������ŁA���ȐӔC�̂��ƂŎg�����Ȃ��G�L�X���Ɨ������Ă��܂��B
�ȏ�܂Ƃ܂�̂Ȃ����e�ɂȂ�܂������A���ꂩ����������������A�����\�ȁu�ۍk�_�@�i�Z�p�v�V�j�v��������A�\�Ȍ���ȗ́E�ȃG�l�E�ȃR�X�g�͔|�����{���A���萶�Y���ێ����Ă��������Ǝv���Ă��܂��B
|
���������ɂ��u���C�G�L�X�v�̍���
�|�{�ɕK�v�ȋ@��̗p��
| ���q�[�^�[�F |
(��)�n���d�C�������@B�^(���p)�@100V�@1.5kW |
| ���T�[���X�^�b�g�F |
(��)�}�g�d�C �_�d�d�q�T�[�� ND-710 �P��100V15A �I�[�v���^(�g�[�p)0���`50��C |
| �����ʊ�i��M�f�W�^�����j |
| ���|���o�P�c�F |
�e���ɕK�v�ȗe�ʂ̂��́i�t�^�t�̂��́j |
|
���C�G�L�X�̍����Ǝg�p�@�̊�{
|
�P�D���C�G�L�X�PL�̎g�p�ޗ�
| �@�@���C�G�L�X�̑f�F |
��������t�i6,000�~/200g+
��������+�Ł\200L���g�p�j |
| �A�@�A�@�@�f�@�@�@�F |
�P�O�� |
| �B�@���C�G�L�X�p�Z�����[�Y�F |
0.5�� |
| �C�@�����F |
�R�Og�A���̓u�h�E���Q�O�� |
| �D�@�G�r�I�X�i�ϕ���g�p�j�F |
4���i��ǂōw���j |
| �E�@�V�@�R�@���F |
�PL |
| �F�@�|�@�F |
�T�O��L(���i���艻�̂��߁A��H 3.5)
���́A�N�G���_����10g�g�p����
�i��ǂōw���j |
�Q�D����
| �@�@�G�r�I�X�@�F |
�Q�O�O��L�̓V�R���łP�O���Ԏϕ� |
| �A�@���@���@�@�F |
�R�O���@�c��̂W�O�O��L�̓V�R���ɓ���h�a |
| �B�@�A�@�f�@�@�F |
�P�O���@�@���@�� |
| �C�@���C�G�L�X�̑f�@�F |
�P���@�@���@�� |
| �D�@�Z�����[�Y�@�F |
0.5���@�@���@�� |
| �E�@���@���@�F |
�@���W�O�Og�̍����t�ɓ���ĂR�T�x������
�S�T�x�����R���ԕێ�����A
�r���Q�A�R��U���E�K�X�������� |
�F �A��Ɠ��̓������łĊ���������A�P�O���Ԏϕ����āA�|�T�O��L���́A�N�G���_�P0�����������ďo���オ��
|
�R�D�g�p�@
|
300�{�ɔ��߂Ď�q���ł̑���┭�董�i�Ɏg�p���܂��B�t�ʎU�z��W���ܑ���Ɏg�p���邱�Ƃ��o���܂��B�_��ƕ��p����Ɣ_��̔Z�x���ɂ��Ă������ȏ�̌��ʂ��ł܂��B�i�Z�������悭�Ȃ邽�߁j
|
�ȏ�
|
|
�ۍk�_�@�A�A�X�J�}��21�̃p���t���b�g�_�E�����[�h�͂����炩�� |
|
�@ |
|
�A�X�J�� �w�ۍk�_�@�x �̏��W�o�^���擾���Ă��܂� |
 �@
�@ |
|
�[��12��A�X�J������|�[�g�[ |
 �@
�@ |